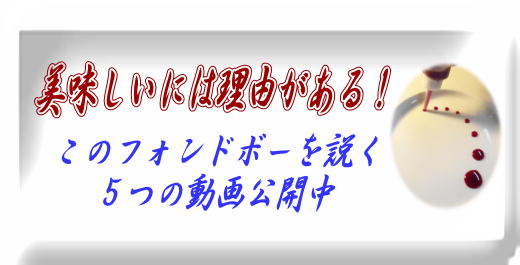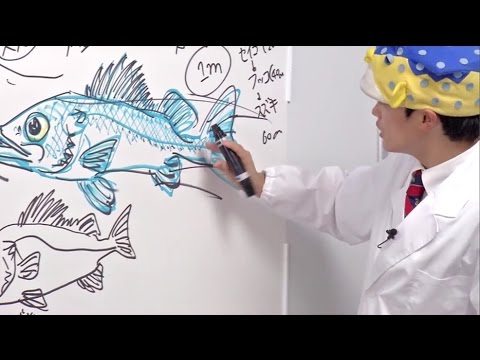
同種の魚を異なる名称で呼ぶ理由には、大きさや外見、生息域、生態の変化などがあります。
例えば、成長の早い魚類では、生まれた当年の魚から2年目、3年目と続くと、
同じ時期に漁獲されたとしても、それぞれの体の大きさが一回り以上異なることがあります。
そのため、商品価値や用途が異なる場合、混同を避けるために異なる名称で呼ぶことがあります。
一方、「出世魚」とは、稚魚から成魚までの成長過程で名前が変わっていく魚のことを指します。
この表現は、武士や学者が出世するにつれて改名する習慣に由来し、「出世魚」と呼ばれるようになりました。
輸入された魚でも、成長に伴って名前が変わるという例はありません。
このような風習は、日本独特の文化や伝統と結びついています。
見た目や大きさ、生体の変化が識別可能なため、同じ種類の魚でも異なる名前で呼ばれることがあります。
また、縁起の良い魚として、祝いの席などで振舞われることもあります。
出世魚の名前が変わる仕組みには決まったルールはなく、地域や文化によって異なります。
例えば、「ブリ」は、地方の呼び方の違いも含めると80種類以上もの名前の変化があるといわれています。
日本近海に生息するブリの稚魚は「モジャコ」と呼ばれ、
成長に伴って「ワカシ」「ツバス」「ワカナゴ」などと呼ばれるようになります。
成長とともに名前を変える魚は、釣り方や店頭での扱いも異なります。
例えば、ブリの場合は成長に合わせて釣り方が変わり、店頭でも成魚と若い魚が並ぶことがあります。
そのため、両方を味わってみることで、魚の成長に伴う味の違いを体感することができます。
出世魚というテーマのページになりましたので、築地を舞台にした面白い映画がありましたので一本紹介したいと思います。
映画 築地魚河岸三代目
「東京築地市場」――日本の台所として知られるその場所で、人々の営みが繰り広げられる。
そこで、大沢たかお、田中麗奈、伊原剛志ら実力派が躍動する姿を描いた映画がある。それが『築地魚河岸三代目』だ。
物語は、エリート会社員の旬太郎が、恋人の実家である築地の仲卸店を手伝うことから始まる。
厳しいプロの世界に足を踏み入れた旬太郎は、やがて会社を辞め、店を継ぐ決意を固める。
これは、商社マンが築地魚河岸の娘を嫁に迎えるために、魚業界に一から弟子入りする物語だ。
原作がしっかりしていることもあり、脚本もよくまとまっている。
笑いあり、涙ありの人情ドラマが見事に展開されている。
そして、映画を見た人々はエンドロールの後に「2009年 シリーズ化決定!!」という文字を見た。
果たして、この物語はどのような続編として成立するのだろうか。原作を知る人ならば、その先が気になることだろう。
音楽も印象的であり、特に「ナニワ何とか」のメロディが耳から離れない。
主人公の旬太郎が築地でどのように成長していくのか、期待されたが、物語はそれほど直接的な描写を与えない。
だが、役者たちの力量は目を見張るものがあり、どの役者も素晴らしい演技を見せた。
そのため、この映画は楽しめるものとなった。サラリーマンが魚市場に飛び込む、恩人へのリストラ通告、
そして市場での努力――これらはまるでドラマのような雰囲気を持ち合わせているようだった。
|
|
ちゃちゃっと作れる「ブリ大根」
フライパンで☆スピードぶり大根☆
by HALE.

材料(2人分)
ぶり / 2~3切れ
大根 / 1/5本
☆水 / 100ml
☆醤油・酒・みりん / 各大さじ3
☆砂糖 / 大さじ2
☆和風だし / 小さじ1
☆生姜の薄切り・ネギの青い部分 / 適量
白髪ねぎ / 適量
レシピを考えた人のコメント
時間がない時にもってこい!下茹でいらずの薄切りぶり大根☆
詳細を楽天レシピで見る→
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
↓↓ ポイントが貯まるレシピ サイト ↓↓
>>最短約 30 秒!▼無料▼会員登録<<
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
お店の味を根底からレベルアップする「KWBフーズのフォンドボー」詳細の動画解説
こんな凄いフォンドボーは市販では見つからない!! プロが見ればひと目でわかる。冷蔵するとゼラチン質で固まっています。動画で確認できます。
この世で一番美味しいビーフシチューが完成しました。煮込み料理で、使う場合は、500gのブック型。この動画の通りに作ってみてください。
業務用は1kgサイズもあります。動画をご参考に。
『KWBフーズのフォンドボー』を使用してソースを作ってみました。けっこう美味しいソースなので他肉料理にも使えます。
それがこの動画です。フォンドボーを使った「ペッパークリームのステーキソース」の作り方。